「応急救護、うまくできる?」その不安を解消!当日の内容と心構え
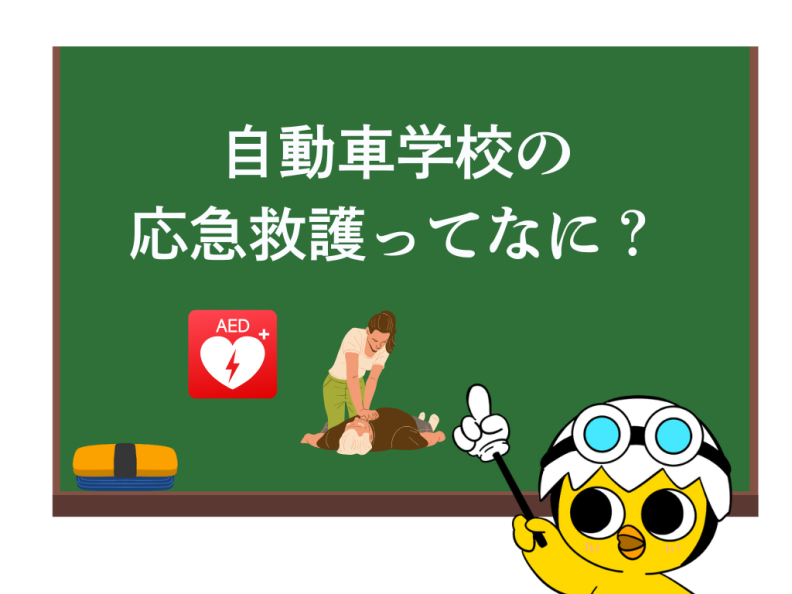
「自動車の免許を取りたいけど、学科教習にある応急救護って具体的に何をするんだろう…」
「もし、本番でパニックになって、うまくできなかったらどうしよう…」
「体力に自信がない自分でも、ちゃんとできるのかな?」
こんにちは!姪浜ドライビングスクールです!これから自動車免許を取得する皆さん、学科教習の「応急救護」に不安を感じていませんか?この記事は、福岡市西区の「姪浜ドライビングスクール」が、長年の指導で培ったノウハウと教習生の皆様のリアルな声をもとに、応急救護の不安や疑問を解消するために作成したガイドブックです!
この記事を読めば、以下のことが分かります。
-
・応急救護教習で具体的に何をするのか
-
・多くの人が感じる不安や疑問点とその解決策
-
・自信を持って教習に臨むための心構え
単なる手順の説明ではなく、あなたが抱える不安に一つひとつ寄り添い、丁寧に解説いたします。この記事は、あなたが安心して教習を受け、そして万が一の時に大切な人の命を守るための「最初の一歩」を力強く踏み出すためのパートナーです。私たちと一緒に、応急救護への不安を自信に変えましょう!
1. そもそも自動車教習の「応急救護」とは?なぜ学ぶ必要があるの?

【なぜ必要?】自動車免許の応急救護|教習で学ぶ目的と重要性を解説
「応急救護って難しそう…」「医療の専門知識なんてないけど大丈夫?」
自動車免許の教習で必須の「応急救護」について、多くの人がそう感じています。しかし、ご安心ください。応急救護の目的は、プロの救急隊が到着するまでの間、命のバトンをつなぐための知識と技術を学ぶことです。
この段落では、応急救護がなぜ重要なのか、その核心を3つのポイントで分かりやすく解説します。
1. 交通事故は他人事ではない!あなたが最初の発見者になる可能性
警察庁の統計によると、交通事故は年間約30万件も発生しています。これは、いつ、どこで、あなたが事故の当事者(加害者・被害者・目撃者)になってもおかしくないということです。
事故現場に最初に居合わせるのは、訓練されたプロではなく、偶然そこにいた「あなた」かもしれません。その時、何もできずに救急車を待つだけでは、助かる命も助からなくなってしまいます。
2. 命を救うタイムリミット!「救命の連鎖」であなたが果たす重要な役割とは
人が心肺停止に陥った場合、救命率は1分ごとに約10%低下すると言われています。救急車の全国平均到着時間は約8,9分。この「空白の時間」を埋めるのが、あなたが行う応急救護です。
そこで重要になるのが「救命の連鎖」という考え方です。
-
・心停止の予防(安全運転や健康管理)
-
・早期認識と119番通報
-
・一次救命処置(←ココが応急救護!)
-
その場に居合わせた人が行う胸骨圧迫(心臓マッサージ)やAEDの使用
-
-
・二次救命処置(救急隊や医師による医療)
教習で学ぶ応急救護は、この連鎖の中で最も重要な「3番目」を担い、プロに命のバトンを渡すための、決定的な役割を果たします。
3. 失敗を恐れないで!あなたを守る「善きサマリア人の法」の精神
「もし処置をして、かえって状態を悪化させたら…」と不安に思うかもしれません。
しかし、日本では悪意や重大な過失がなければ、善意で行った救護活動の結果について法的な責任を問われないという考え方があります。
大切なのは、完璧な処置ではなく「助けたい」という気持ちで、勇気を出して行動することです。
2. 応急救護はいつ受けるの?教習全体の流れとスケジュール

「応急救護が大切なのは分かったけど、具体的にいつ、どんなタイミングで受けるの?」という疑問にお答えします。免許取得までの詳しいステップは「教習の流れ」ページでもご確認いただけます。
応急救護処置教習は、自動車教習の第二段階で受講が義務付けられている学科教習です。そもそも第一段階、第二段階とは
- 第一段階: 教習所内のコースで、基本的な運転操作や交通ルールを学び、修了検定と仮免許学科試験に合格して「仮免許」の取得を目指す段階です。
- 第二段階: 仮免許を取得し、いよいよ実際の路上での運転練習がメインとなる段階です。高速教習や、危険を予測するディスカッション形式の教習などもここに含まれます。
応急救護は、この第二段階の学科教習の一つとして組み込まれています。第二段階の路上教習では、予期せぬ歩行者の飛び出しや、他車の危険な動きなど、ヒヤリとする場面に遭遇することもあるでしょう。そうした実践的な運転と並行して、万が一の事態に備えるための応急救護を学ぶことで、「自分は責任あるドライバーになるんだ」という自覚がより一層深まるのです。
応急救護処置教習の時間と場所、そして予約について
- 時間: 3時限連続で実施されます(1時限=50分)。間に10分間の休憩を挟みながら、合計で2時間30分かけてじっくりと学びます。
- 場所: 応急救護専用の機材が揃った教室で行います。広々とした空間で、安心して実技に集中できます。姪浜ドライビングスクール校内の施設案内はこちら。
- 予約: 応急救護教習は、複数の教習生が同時に受講するグループ教習のため、事前の予約が必要です。人気の時間帯は埋まりやすいため、第二段階に進んだら早めに学科教習のスケジュールを確認し、予約を入れることをお勧めします。
「3時間も!?」と最初は長く感じるかもしれませんが、座学だけでなく、実際に体を動かす実技が中心なので、ほとんどの教習生が「あっという間だった」「思ったより楽しかった」という感想を抱きます。ぜひリラックスして参加してくださいね。
3. 【ガイド】応急救護教習の全貌をステップ・バイ・ステップで徹底解説!

ここからは、いよいよ本題です!皆さんが最も気になっているであろう、3時間にわたる応急救護教習の具体的な内容を、当日の流れに沿って、指導員のワンポイントアドバイスも交えながら詳しく解説していきます。
【第1時限目:ガイダンスと基本知識のインプット】
最初の時間は、主に座学から始まります。まずはリラックスしてもらうために、指導員から教習全体の流れや目的について、改めて丁寧な説明があります。その後、多くの場合、交通事故の現実や救命処置の重要性を伝えるための教材(DVDなど)を視聴します。
少しシリアスな内容かもしれませんが、これは「なぜ自分たちがこれから3時間かけてこれを学ぶのか」を自分の中に落とし込み、真剣に取り組むための大切な時間です。
【第2・3時限目:実践!見て、触って、動いて覚える実技訓練】
ここからが本番!グループに分かれ、いよいよ実技訓練のスタートです。
事故現場や急病人がいる場面を想定した訓練です。パニックにならず、冷静に行動するための手順を体に叩き込みます。
- 周囲の安全確認
事故現場で、傷病者を発見しても、すぐに駆け寄ってはいけません!まずは自分の安全を確保することが最優先です。「二次災害の防止」は救護活動の絶対的な鉄則。後続車はいないか、ガソリン漏れで引火の危険はないか、上から何かが落ちてこないかなど、周囲を冷静に確認します。 - 傷病者への声かけと意識の確認
安全が確認できたら、傷病者の耳元に近づき、「大丈夫ですか?わかりますか?」と、優しく、しかしはっきりと呼びかけながら、肩を軽く叩きます。この時、頭を揺さぶるなど、体を激しく揺さぶってはいけません。頸椎などを損傷している可能性があるからです。 - 大声で応援を呼び、役割分担を明確にする!
呼びかけに反応がなければ、すぐに助けを求めます。「誰か来てください!人が倒れています!救急車をお願いします!」と、ためらわずに大きな声で叫びます。
協力者が来てくれたら、ここが重要です。「そこの青い服のあなた、119番通報をお願いします!」「そちらの女性の方、近くにAEDがあれば持ってきてください!」と、具体的に人を指差し、役割を明確にお願いします。「誰か」と曖昧にお願いすると、皆が遠慮してしまい、誰も動いてくれない「傍観者効果」が起こりがちです。 - 呼吸の確認(10秒以内)
傷病者の胸や腹部の上がり下がりを「10秒以内」で確認します。この時、しゃくりあげるような、途切れ途切れの呼吸(死戦期呼吸)が見られることがあります。これは心停止のサインの一つであり、「普段通りの呼吸ではない」と判断します。
この一連の「観察」は、わずか数十秒の間の出来事です。訓練では、この流れを何度も繰り返し練習し、無意識にでも動けるレベルを目指します。
救命の要!胸骨圧迫(心臓マッサージ)
「普段通りの呼吸なし」と判断した場合、ただちに胸骨圧迫を開始します。これが救命の鍵を握る最も重要な手技です。
- 圧迫する場所: 胸の真ん中にある、胸骨という硬い骨の下半分。左右の乳首を結んだ線の真ん中が目安です。
- 手の組み方: 片方の手の付け根を圧迫部位に置き、もう片方の手をその上に重ねます。指を組むと力が安定します。
- 姿勢: 傷病者の真横に膝立ちになり、肘をまっすぐ伸ばして、肩が手の真上に来るようにします。そして、自分の上半身の体重をかけるように垂直に圧迫します。腕の力だけで押そうとするとすぐに疲れてしまいます。
- 強さ(深さ): 胸が約5cm沈む強さで。これは思った以上に力が必要です。なぜなら、胸骨の下にある心臓を直接圧迫し、全身に血液を送り出すポンプの役割を代行するためです。
- 速さ(テンポ): 1分間に100~120回という速いテンポで、絶え間なく続けます。よく例えられる「アンパンマンのマーチ」のリズムがちょうどこの速さです。
教習では、「レサシアン」と呼ばれる人間の上半身を模した訓練用の人形で練習します。この人形は、圧迫の深さやテンポが適切かどうかを音や光でフィードバックしてくれる高機能なものもあり、自分の手技が正しいか客観的に確認できます。(自動車学校により人形は異なります)
「こんなに力が必要なんだ!」「1分も続けると汗だくになる…」と、ほとんどの教習生がその大変さを実感します。だからこそ、周りの人と協力し、「1、2、3…28、29、30、交代!」と声をかけ合い、1〜2分で役割を交代しながら質の高い圧迫を続けることが重要なのです。
AED(自動体外式除細動器)の使い方
協力者がAEDを持ってきたら、すぐに使用します。
「医療機器なんて、素人が使っていいの?」と心配になるかもしれませんが、全く問題ありません。AEDは、電源を入れると音声ガイダンスが使い方を最初から最後まで、すべて丁寧に指示してくれるため、誰でも簡単に、そして安全に使えるように設計されています。
- 電源を入れる: ケースから取り出し、電源ボタンを押します。
- 電極パッドを貼る: 傷病者の衣服をはだけさせ、パッドに描かれているイラストの通りに、胸の右鎖骨下と左脇腹の素肌に直接、しっかりと貼り付けます。(※体が濡れていれば拭き、貼り薬があれば剥がす、といった注意点も学びます)
- 心電図の解析: パッドを貼ると、AEDが「体に触れないでください」とアナウンスし、電気ショックが必要かどうかを自動で解析します。私たちはAEDの指示に従うだけです。
- 電気ショック: ショックが必要な場合は「ショックが必要です。充電しています。体から離れてください」とアナウンスされ、充電完了後にショックボタンが点滅します。救助者全員が傷病者から離れていることを確認し、「離れて!」と声をかけ、点滅しているボタンを押します。
ショック後も、AEDの指示に従い、ただちに胸骨圧迫を再開します。教習では、訓練用のAEDを使って、この一連の流れを何度も繰り返し練習するので、いざという時も自信を持って操作できるようになります。
その他の応急手当(止血法など)
心肺蘇生のほか、交通事故で起こりやすい出血への対処法も学びます。特に重要なのが直接圧迫止血法です。清潔なガーゼやハンカチなどを出血している傷口に直接当て、その上から手のひらで強く圧迫し続ける、最も基本的で効果的な止血法です。
(参考)人工呼吸について
以前は胸骨圧迫30回と人工呼吸2回をセットで行うのが標準でしたが、近年、新型コロナウイルス感染症の流行などを背景に、一般市民による人工呼吸は、ためらいがある場合や、訓練を受けておらず自信がない場合は省略し、胸骨圧迫を絶え間なく続けることが強く推奨されています。教習では方法を学びますが、実際の現場では胸骨圧迫を優先することが命を救う上で最も重要だと覚えておいてください。
4. 応急救護を学んだ先輩たちの声【姪浜DS卒業生体験談】

実際に教習を受けた先輩たちは、どんなことを感じたのでしょうか?ここで、当校を卒業した方々から寄せられた声の一部をご紹介いたします。
(20代・女性・Aさん)
「入校前は応急救護が一番の不安でした。血とか苦手だし、自分にできるわけないって。でも、実際にやってみたら、人形相手だし、先生がすごく丁寧に教えてくれるし、何よりグループのみんなと『せーの!』で声を出しながらやるのが意外と楽しくて。3時間があっという間でした。今では、もしもの時、何もしないで後悔するよりは、学んだことをやってみようって思えるようになりました。」
(19歳・男性・Bさん)
「正直、最初は『めんどくさいな』って思ってました(笑)。でも、胸骨圧迫が想像以上にキツくて、これを救急隊が来るまで続ける大変さを実感しました。AEDも初めて触ったけど、機械が全部しゃべってくれるから本当に簡単で。免許のためだけじゃなくて、普通に生きていく上で、知っておくべきことなんだなって考えが変わりました。受けてよかったです。」
5. 不安を完全解消!姪浜ドライビングスクールの応急救護Q&Aコーナー

ここでは、教習生の皆さんから特によく寄せられる質問に、私たち指導員がズバッとお答えします!
この他にもご不明な点があれば、「よくあるご質問」ページもぜひご覧ください。
Q1. うまくできなかったら落とされる?厳しい試験はあるの?
A1. ありません!ご安心ください。 応急救護教習は、皆さんを試すための試験ではありません。大切なのは、完璧にできることよりも、「命を救いたい」という気持ちを持って、真剣に教習に取り組む姿勢です。指導員は、皆さんが手技をマスターできるよう、一人ひとり丁寧にサポートします。もし分からなければ、何度でも手を挙げて質問してください。目的は、皆さんに自信を持ってもらうことです。
Q2. 当日の服装や持ち物で気をつけることは?
A2. 動きやすい服装がベストです。 胸骨圧迫など、体を動かす実技が中心となるため、スカートや胸元の大きく開いた服、ダメージジーンズ、ハイヒールなどは避けてください。パンツスタイルにスニーカーといった、体育の授業に参加するような服装が理想的です。持ち物は、基本的に筆記用具程度で大丈夫ですが、詳細はご入校の際にご案内しています。
Q3. 女性でも男性と同じように胸骨圧迫できますか?体力に自信がありません…。
A3. 全く問題ありません。 胸骨圧迫は腕力ではなく、体重をかけるのがコツです。小柄な方でも、正しい姿勢を身につければ十分に圧迫できます。そして何より、実際の現場でも教習でも、救護は一人で行うものではありません。必ず周囲と協力し、1〜2分で役割を交代しながら行います。体力や性別に関係なく、誰もがチームの一員として貢献できるので、安心してください。
6. まとめ:安心して応急救護に臨み、命を守れるドライバーへ

今回は、自動車免許取得における応急救護処置教習について、その目的から具体的な内容、先輩たちの声、そして皆さんの不安にお答えするQ&Aまで、徹底的に解説してきました。
- 応急救護は、プロに命のバトンをつなぐ「救命の連鎖」の超重要な一部
- 教習は第二段階で行う3時限連続の実技中心のプログラム
- 内容は「観察」「胸骨圧迫」「AED」がメインで、高機能な人形でリアルに練習
- 試験はなく、グループで協力して行うので体力や知識に不安があっても大丈夫
- 学んだ知識は、運転中だけでなく、人生のあらゆる場面で役立つ一生モノのスキル
この記事を読んで、応急救護への漠然とした恐怖や不安が、少しでも「自分にもできそう」「やってみよう」という前向きな気持ちに変わっていたら、私たちにとってこれほど嬉しいことはありません。
応急救護で学ぶことは、技術だけではありません。それは、人の命の重さを知り、交通社会の一員としての責任を自覚し、そして何よりも「見て見ぬふりをしない」という優しさと勇気を育む、人間教育の場でもあるのです。
姪浜ドライビングスクールでは、経験豊富な指導員が、一人ひとりの不安な気持ちに寄り添い、確かな知識と技術、そして「行動する勇気」を育む教習を約束します。
福岡市西区、姪浜周辺で自動車免許の取得をお考えなら、まずは詳しい料金プランをご確認の上、ぜひ一度、姪浜ドライビングスクールへご相談ください。アットホームな雰囲気の中で、私たちと一緒に、安全で楽しいカーライフへの、そして、誰かの命を守れる頼もしい大人への第一歩を踏み出しませんか?
スタッフ一同、あなたの挑戦を心から応援しています!
▼まずは資料を見てみたい方へ
無料の資料請求はこちら
▼入校に関するご相談・お申し込みはこちら
入校お申し込みフォーム
▼お電話でのお問い合わせもお気軽にどうぞ!
TEL: 092-881-1234
(受付時間:平日9:00~20:40)
▼学校の場所はこちらでチェック
アクセスマップ




